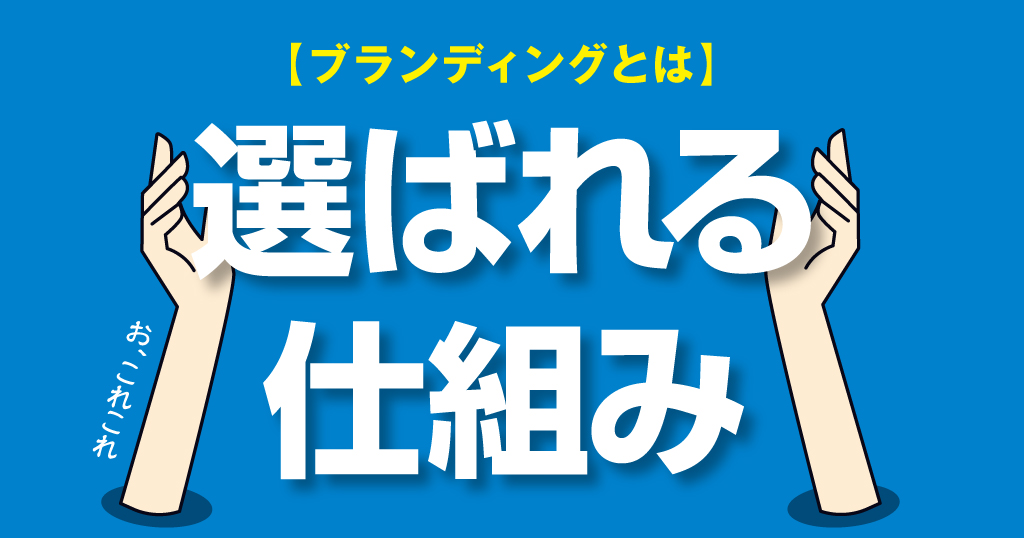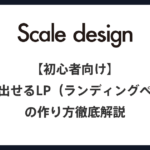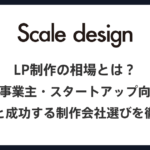こんにちは。今回「ブランディング」というテーマについて考えたいと思います。
・新サービスの成果がなかなか出ない。
・商品には自信があるけれど、売上が思うように伸びない。
・広告を出しても、手応えがいまひとつ。
・気づけば“価格競争”に巻き込まれている。
もし、どれかひとつでも「あるかも…」と思ったなら、
一度“ブランディング”という視点を取り入れてみると新しい発見があるかもしれません。
「ブランディング=かっこよく見せること」ではない
「ブランディングって、ロゴとか色味とか、見た目を整えることでしょ?」
そう思っている方もいるかもしれません。たしかにそれも一部ではありますが、本質はそこではありません。
ブランディングとは「なぜ、この商品を買うべきか?」という“選ばれる理由”を、顧客の心に植え付けることです。
たとえば、同じような機能を持ったバッグが2つ並んでいたとします。
- 1つは「丈夫で収納力のあるバッグ」
- もう1つは、「PCや資料、出張時に必要なものをスマートに収納できるビジネスバッグ」
どちらが購入後の自分をイメージしやすいでしょうか?

前者は“よくある情報”を伝えており、どんなシーンでも使えそうです。
後者は“荷物をスマートに収納したい出張の多いビジネスマン向けのバッグ”というイメージが浮かびますね。
これが「選ばれる理由」の差です。
誰のための商品なのか?どんな課題を解決してくれるのか?
といったことが盛り込まれていると価格やスペック情報だけでなく、
新しい比較のベクトルが生まれるわけです。
この “誰のどんな悩みに応えるのか”を可視化していくことがブランディングにとって、大事なポイントになってきます。
言葉のルーツから考えてみる
さらに理解を深めるために少し角度を変えて「ブランディング」の語源を見ていきましょう。
ちょっと意外かもしれませんが、「ブランド(brand)」という言葉の語源は、古ノルド語の brandr、意味は「焼きつける」。
もともとは家畜に焼印を押して「これは自分の所有物だ」と示すためのものだったといわれています。

この“焼印”は単なる識別マークにとどまらず、やがて「この焼印がある家畜は信用できる」「この牧場の牛なら安心だ」といったように、品質や信頼の象徴としての意味を持つようになっていきます。
つまり、ブランドのルーツって、「これ、ウチの牛です」を主張するマークから、「ウチの牛は安心で安全ですよ」とメッセージを伝える印に進化していったわけですね。
そして現代、このブランドという言葉は、印(ロゴ)とメッセージ(キャッチコピー)が合わさり、「なぜこの商品・サービスが存在し、誰のどんな課題を解決するのか、そしてこの商品・サービスが社会にどういった価値をもたらすのか」といったことまでを伝えるものへと進化してきました。
このように言葉のルーツから探っていくと
ロゴは“焼印の形”、キャッチコピーは“メッセージ”そしてそれが人の記憶に残り、ストーリーを伝えるシンボルとなっていったわけですね。
この語源の歴史から紐解いてみても、冒頭でお伝えした「ブランディング=見た目をかっこよくする」ということが本質ではないということが見えてきます。
事業にどのように落とし込むのか
では今みなさんが展開されている事業にどのようにこの「ブランディング」を反映してけばいいのでしょうか?
ここでは私がよくクライアント様に質問する項目をあげましたので、
一度一緒に考えてみてください。
- なぜこのサービスを始めたのか?
- 競合と何が違うのか?(機能や価格以外で)
- このサービスでお客様はどんなハッピーを享受するのか?
- さらにその先にお客様はこのブランドに、どんな未来を期待するのか?
このような問いの答えをまとめて、自社のWebサイト、営業トーク、パンフレット、SNS投稿など
ユーザーとのあらゆる接点で“一貫して語られているか”が、ブランディングの要です。

この、「メッセージ」を意図的に価値のある設計にすることがブランディングの核心ともいえます。
これは広告に大きな予算を投じる前に、まずは整えておきたいポイントです。
どのビジネスフェーズで必要になるのか?
「ブランディングなんて、売れてから考えればいい」
そう思っている方も多いかもしれません。
私たちもクライアント様からの依頼の大半は後付けでブランディングを設計していくことがほとんどです。
しかし本来は“最初に設計しておくべき経営戦略”です。
“誰のどんな課題をどう解決するのか”このテーマは商売をしていく上で利益を生み出す軸そのものになりますから。
価格競争に巻き込まれないための施策として早めに構築するに越したことはありません。
しかしながら、ご安心ください。初めから何もかもが完璧に設計されて、そのまま綺麗に走り切れるケースなんて、まあありません!
今これほどあふれんばかりの情報と変化の早い時代にそんな偉業を成せる強運の持ち主はごく一部でしょう。
そこで成長フェーズごとに必要なブランディングを切り分けてその役割を考えていきます。
ここでは4つの典型的なビジネスフェーズに分けて、それぞれのステージで「何に取り組むべきか?」を具体的に考えてみました。
【1】創業・立ち上げフェーズ
キーワード:差別化/理念の明文化/ポジショニング
創業期には、知名度も実績も限られており、「何屋なのか」が曖昧な状態になりがちです。
この段階で最も重要なのは、「誰に、どんな価値を、なぜ届けるのか」を明確にしておくこと。
ここを曖昧にしたまま進むと、後から商品がブレたり、
メッセージが一貫しなかったり“何をしてくれるかよく分からない会社”という問題に直面しがちです。
▶やるべきこと
- 簡単なものでもミッション、ビジョン、バリュー(MVV)の言語化
- ブランド名・ロゴ・カラー・トーンの整備
- 小規模でも良いので、社内外共有用のビジュアルガイドを用意
このフェーズのブランディングは、いわば「事業の土台づくり」。
需要を掘り起こしながら目先の売上を作りつつ、
“これからの成長を支える軸”を丁寧に設計する時期です。
【2】商品/サービス拡張フェーズ
キーワード:統一感/ブランド資産の積み上げ
事業が進み、商品ラインやサービスの数が増えてくると、つい全体像を考えないまま“個別最適”に走りがちです。
たとえば、A商品の資料は高級感、B商品のLPはポップ…といったように、ブランド全体の印象がバラバラになってしまうケース。
このフェーズでは、「ブランド全体としてどう見えるか」を整える必要があります。
ブランドの共通項=“らしさ”を設計し直し、全体の統一感を持たせたり、思い切ってターゲットごとにブランドをセグメントするといったことも必要なフェーズです。
▶やるべきこと
- ブランドアーキテクチャ(親ブランドと子ブランドの関係性)を設計
- ターゲット別のLPや販促物を、ブランドの世界観に沿って作成
- ブランドマニュアルやブランドバイブルの作成(内外共有用)
ここでは全体設計のための個別を最適化をしていくイメージです。
たとえば、稼ぎ頭となっているAという商材の補完商材Bを扱うことで、同カテゴリー内のターゲットの入り口を増やしたり、
売れ行きの悪いCという商材の打ち出しを変えたり、あるいは廃盤にしたり、全体の見え方を意識しつつ個別の最適化を行ない、
ブランド全体の方向性に合わせてをチューニングしていくようなイメージです。
【3】スケール・採用強化フェーズ
キーワード:一貫性/社内浸透/対外信頼
ある程度の規模になってくると、課題は“外への発信”だけではなく、“内側の足並み”にも現れます。
たとえば、部署ごとにブランドの解釈が違っていたり、協力会社によって制作物のトーンがバラバラだったり…。
このフェーズでは、「ブランドを守る文化」と「浸透の仕組み」が必要になってきます。
経営者や創業のボードメンバーの頭の中にしかないブランド像を、
会社全体で共有できる状態に変えることが、拡大期の安定成長につながります。
▶やるべきこと
- 社員向けブランドトレーニングや、理念研修の実施
- 採用ページ・IR情報などの表現もブランドに合わせて再設計
- デザイン・言語などのチェック体制を構築し、ブランド品質を守る
この規模のブランドになってくると「見た目の統一」ではなく、「思想の統一」が問われてきます。
【4】再構築・リブランディングフェーズ
キーワード:見直し/再定義/再成長
市場の変化、競合の進化、顧客の世代交代などによって、「これまでのブランドが、いまの時代と少しズレてきた」という瞬間が訪れます。
これほど変化の早い時代です。創業期に打ち立てたビジョンが永年続くといったことは稀で、時代に合わせて変革していかなければいけません。
この今まで通用していたものが通用しなくなった。といった現象に対応するためにリブランディングが必要になってきます。
過去の資産を大切にしながらも、「これからの時代に適応し選ばれる姿」へと再定義していくのが、このフェーズの役割です。
▶やるべきこと
- 社内外へのヒアリングや調査を通じたブランドリサーチ
- ブランドパーソナリティ(性格・立ち位置)の再定義
- ロゴ、UI、キャッチコピー、トーン&マナーの刷新
ここでは、「変えない部分」と「変えるべき部分」の線引きが鍵になります。
大切なのは、“自分たちの本質を残したまま、新しい表現で語る”ということ。
まとめ:ブランドは“成長段階ごとに問い直す経営資産”

ブランドは一度つくってしまえばあとは自動で稼いでくれるものではありません。
むしろ、「どのフェーズでも、今の状態に合わせて問い直し、育てていくもの」と私たちは考えています。
逆に言えば、成長の段階に合わせてブランディングの役割をきちんと見極めておけば、
事業のブレも、迷いも、機会損失も最小限に抑えることができます。
ブランディングは“デザインの話”ではなく、経営をスムーズに、そして力強く前進させるための羅針盤ともいえます。
今、あなたの事業にとって必要な“ブランディング”はどのフェーズですか?